こんにちは!Henyoharo Percussionの純太郎です!
第10曲となった楽曲分析シリーズですが、初めて三部形式が登場しました。
この記事では、二部形式と三部形式の違いや見分け方について書いていきます!

和声分析
いつもは形式を先に分析していますが、今回は和声から見ていきましょう!

まずC durではじまり、その後G durに転調、最後は再びC durで戻ってきます。
この調の移り変わりは後述する形式と一致しています。
楽譜中に「倚音(いおん)」という言葉を書き込んでいます。
これは非和声音の一種なのですが、今回は説明を省きます。
トニック・ペダル
ペダル・ポイントについてはこちらの記事で詳しく説明しています!

三部形式!

それでは形式を見ていきましょう。
楽譜に書き込んでいるとおりなのですが、
冒頭からリピート記号までの16小節間が大きなA
リピート記号から16小節間が大きなB
そして残りの16小節間が大きなA’
となります。
それぞれの部分はさらに2つずつに分けられるので、全体を見ると
A[a-b]-B[c-c’]-A'[a-b’]
となり、大きな部分が3つあるので、三部形式ということになります。
二部形式との違い
文字通りなのですが、二部形式は大きな部分が2つです。
例)
A[a-a’]-B[b-a”]
A[a-b}-B[c-b’]
*今回から記号の付け方を変更しました。紛らわしくてすみません・・・!
見分け方ですが、最初はなかなか難しいです。
単純な曲であれば、各部分は大体同じくらいの小節数になるので、そこから判断すると良いかもしれません。
*BがAの倍の長さになったら三部形式を疑う
まとめ
前回までは全て二部形式でしたが、ついに三部形式が登場しました。
三部形式になると曲の内容も充実してきて、曲中の変化も豊かになってきます。
これからどんどん分析も楽しくなるので、一緒に勉強していきましょう!

*HENYOHARO PERCUSSIONではオンラインで受けやすい理論のレッスンも行っております。
興味を持たれた方は是非体験レッスンを受けてみてくださいね!
また、アレクサンダー・テクニークのレッスンモニターも募集しております。詳しくは下記記事を御覧ください!







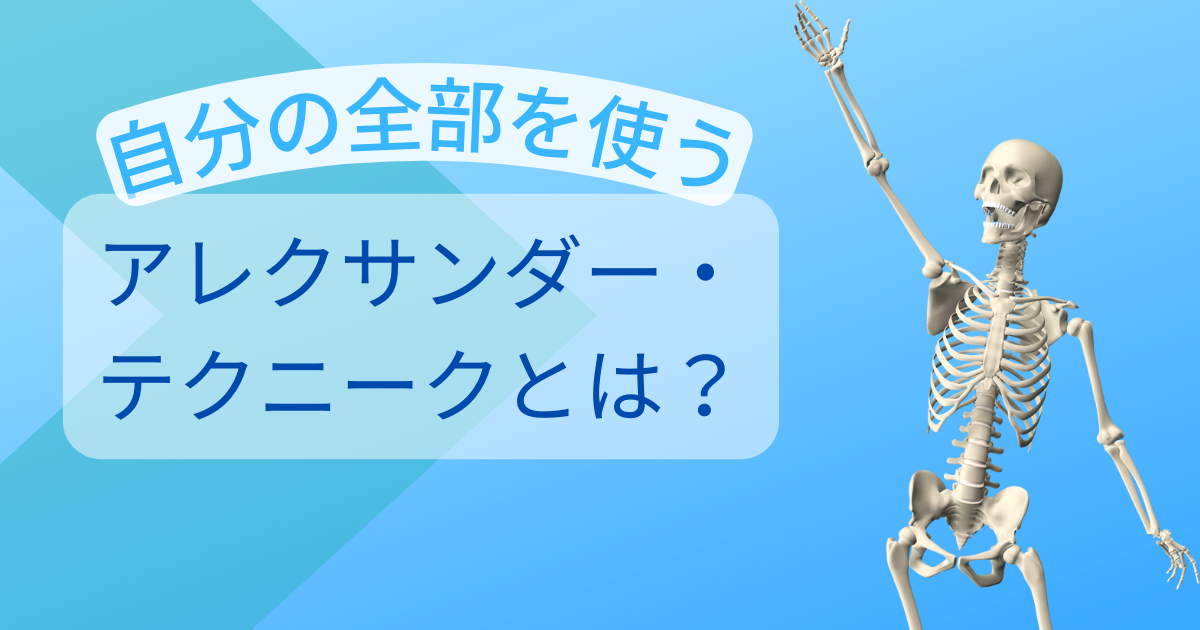
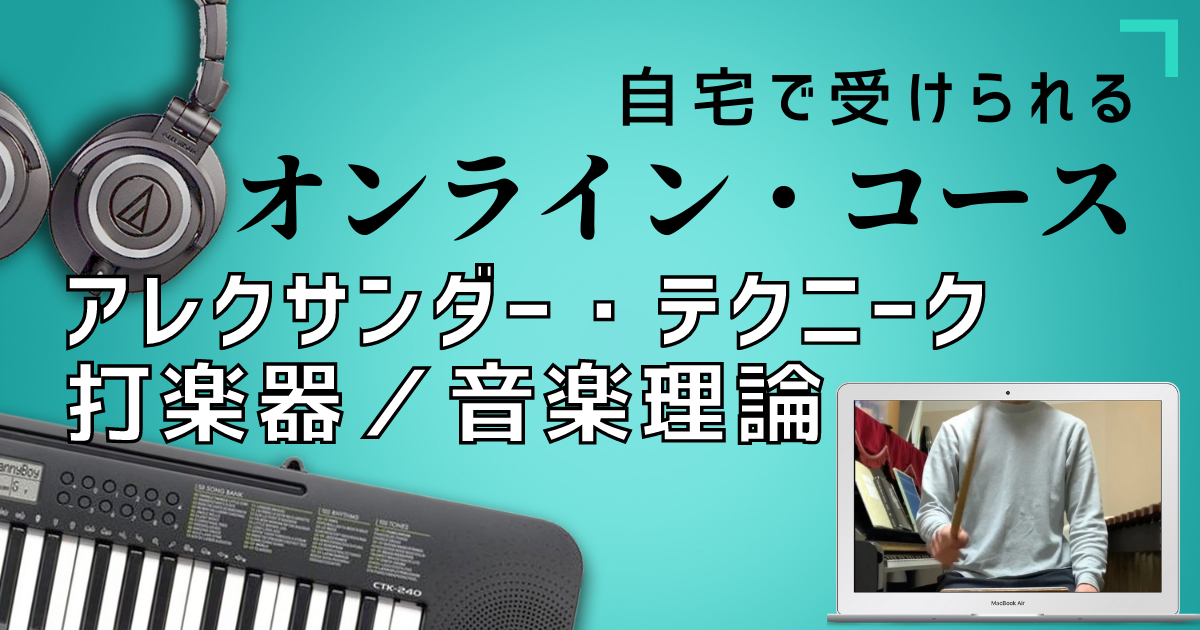

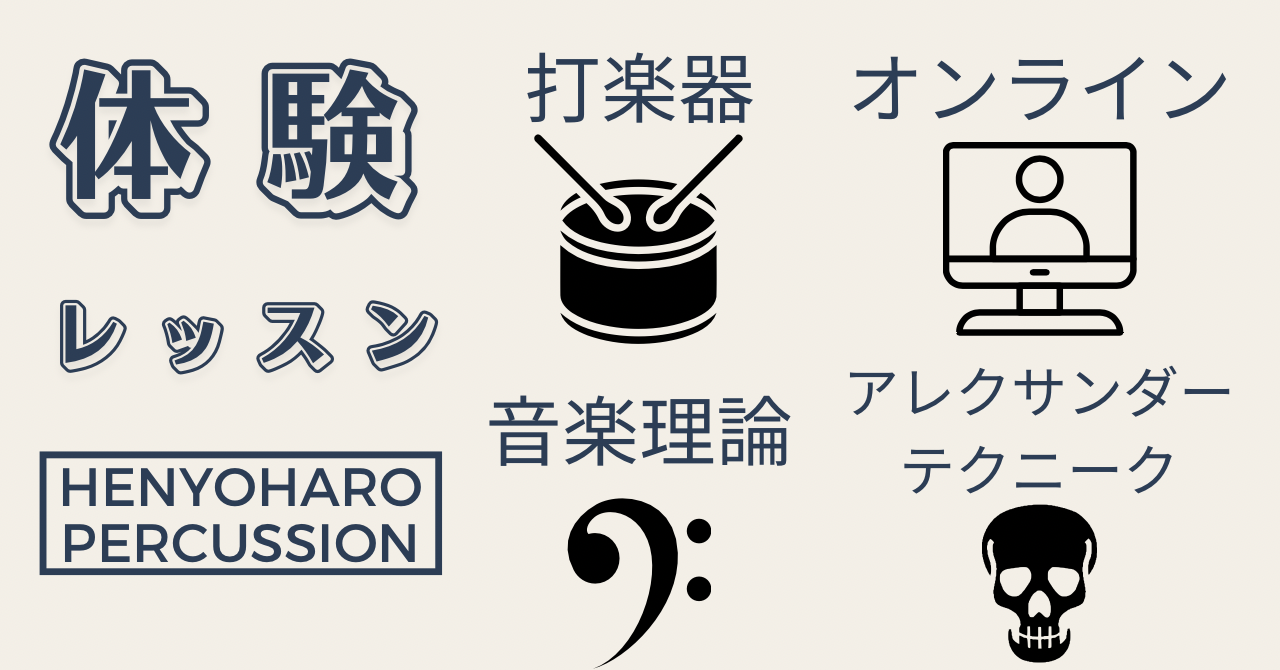


コメント